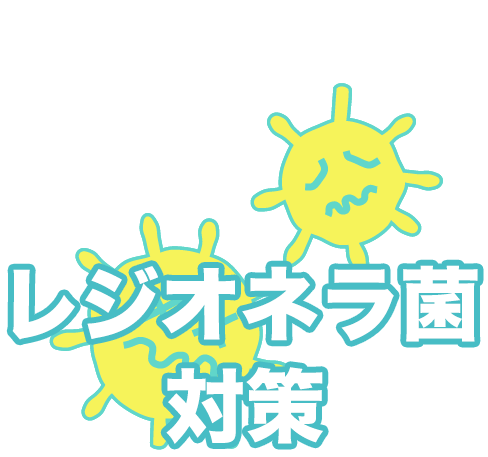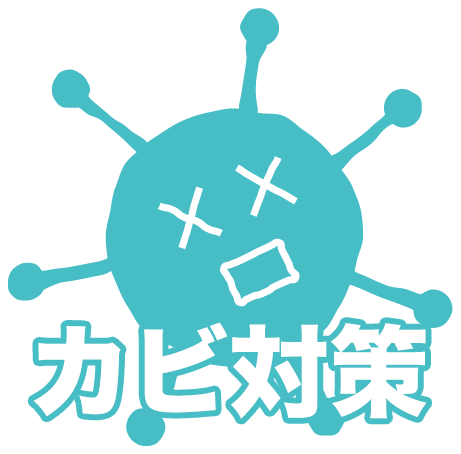動画で見るCSC工法
カビ対策
どんなに掃除しても取れない黒ずみ。汚れではなく「カビ」です。
カビを除去して安全な環境を維持しませんか?
清掃しても黒く残って擦っても取れない、そんな経験がありませんか。
清掃後も残る黒ずみはただの汚れではなく、ほとんどが “黒カビ” です。
昨今、「菌」・「臭い」に対する問題意識は高まりを見せており、環境の健康への影響やカビと癌の関連性などが注目されています。
特にこうしたカビの問題は、衛生面に特に気をつかう食品加工の分野においては死活問題にもなりかねません。
毎日清掃を行っている工場においても、天井裏、スケルトンの柱裏、吸排気ダクト内など、気付かれにくい場所で黒カビが発生し、見過ごされてしまっていることも少なくありません。
カビ・菌対策専門のCSCでは、3年保証、6年保証の2つのコースをご用意し、安心安全の衛生環境の実現を保証いたします。
お気軽にご相談ください。

湿度の高いところは要注意!カビが繁殖する仕組みとは?
カビの繁殖の仕組み
水を扱う環境の中で、工場は最もカビが繁殖しやすいことをご存じですか。
高い湿度に加え、チリやホコリといったカビの栄養源が豊富に供給されるため、繁殖にはもってこいの場所なのです。
カビは、空気中に浮遊する小さな「胞子」と細い糸のような「菌糸」で成り立ちます。
初めのうちは肉眼では見えないほど小さな胞子となって空気中を浮遊していますが、やがて温度・湿度・栄養などの条件が整った場所に付着し、菌糸を伸ばしながら成長します。私たちの目で”カビが生えている”と認識できるのは、菌糸が成長し、幾重にも重なり合った状態になってからです。
ですから、一見、カビが生えていないと思っているところでも、実はカビが存在している場合があります。
天井裏などの隠れた場所からカビの胞子が撒き散らされることで繁殖が広がるだけでなく、食品に入り込んでしまうことも考えられます。
目で確認できる状態になった頃にはかなり広がっていると考えられるため、早期に対策を行うことが重要です。
見えない場所にもカビが…CSC独自の工法で短期間に徹底除菌
「天井」の見えないカビに注意
天井には本当にカビはいないのか?この疑問を確かめるために天井のカビ実態の調査を開始しました。
その結果、調査した25箇所の約5割で、“肉眼では確認できないカビ”が検出され、その他肉眼でカビが確認できた場所も合わせると、調査対象の約8割でカビが検出されるという結果に。
特に注意すべき場所は“天井”です。
多くの場合天井は、壁や床に比べてカビの栄養分となる汚れが付着しにくいため、菌糸が成長できず、細かな胞子を空気中に放つことで繁殖を図ります。やがてそれらの胞子は、壁や床といった栄養(汚れ)の豊富な場所に付着し、成長します。
そのため、壁や床などカビの見えやすい場所を綺麗にしても、天井などの見えない場所から放出されるカビをきれいにしない限り、またすぐにカビが繁殖してしまう恐れがあります。
ニオイがほとんどなく、短期間で終えられる「CSC工法」
あらゆる場所に発生するカビを除去するにあたって、CSCでは新たに「CSC工法」と呼ばれる手法を開発しました。
天井裏はもとより、吸排気ダクトから壁、床など空間の隅々まで除菌成分を行き渡らせ、カビ胞子の活動を抑制することで除菌します。
また、CSCの特殊工法はニオイがほとんど出ず、工事を短期間で終えられるため、工場の稼働をストップさせることもありません。
3年保証、6年保証の2コースをご用意し、安心安全な環境をご提供します。
●3年保証…メンテナンスなし、保証期間内に作業(一部有料)
●6年保証…メンテナンス基本料金あり、年3回の定期検査・報告・保証期間内に無料作業
カビの実態
カビの生態と健康被害
カビとは
カビは汚れのように見えますが、微生物の一種で真菌というグループに属する糸状菌で、キノコや酵母もその仲間です。
カビは、湿度・温度・酸素・栄養(エサとなる有機物)の条件が整えば胞子が発芽して菌糸を伸ばし、菌糸体へと成長します。
私たちが日常生活の中で見つけられるのは「菌糸体」と呼ばれるカビの集合体だけです。菌糸体まで成長したカビは黒くなった表面をキレイにしても菌糸が奥に隠れているため、またすぐにカビが生えてきてしまいます。

カビの発生場所
カビの発生する箇所には共通点があります。カビも生物の一種なので酸素・栄養・水分が必要です。
最近は、湿度の高い場所に生える好湿性カビに加え、乾いた場所にも発生する耐乾性カビも増えています。
店舗
⇒作業場、冷蔵・冷凍庫周りの壁面、柱、売場天井など。
住宅
⇒天井、屋根裏、建材、クロス、カーペット、窓、屋根・外壁、エアコン、浴室、軒下、台所
発生要因
⇒温度:-5℃~30℃ (25℃~30℃)
⇒湿度:80%以上
⇒栄養:有機物、無機物
建物の構造上の要因
⇒通気性が悪く、機密性の高い建物
⇒建物内の温度差が大きい
⇒湿気の溜まりやすい構造
⇒防カビ対策がされていない
カビと健康被害
住まいに生えたカビをそのまま放っておくと、いずれ勢力を増し、知らない問にその家で暮らす人の健康を害すことがあり、危険です。
カビの健康被害には、アレルギー喘息、シックハウス症候群、皮膚炎などがありますが、これらはカビの健康被害のほんの一部にすぎません。
病院に行くほどではないけれど体がだるく、微熱が続く…
風邪を引いているわけでもないのに瀕繁に咳が山る…そんな症状も、室内に飛んでいるカビの胞子が原因であることがあります。
私たちの生活をカビを始めとする微生物被害から守るには、徹底的な “除カビ” で奥に隠れているカビまでしっかりと取り除き、さらにカビを生えにくくするための “防カビ” を行うことが重要です。この二つの対策を徹底して、快適な生活環境を手に入れましょう。

カビの現状
●工場・店舗などでのカビの現状
食品工場会社、ス-パ-関係、ファミリーレストラン、他厨房使用店等の現場ではカビが天井、壁、床及び換気、排気本体とダクト管に付着していることが多くあります。
カビの胞子が空気中に浮遊し食品等に付着する恐れがありますが、気付かれにくい場所などは見過ごされてしまうことも。
換気、給気のダクト管の中はゴミ、油、ヘドロの付着があり、カビの繁殖に適した環境が提供されているため要注意です。
●家庭でのカビの現状
断熱性・気密性に優れた住宅が増え、快適な生活環境が整えられた昨今においては、こうした快適空間がダニやカビといった健康被害をもたらす生物の温床となっていることが問題視されています。こうした生物は、アレルギー、アトピー性感染症、喘息を引き起こす要因としても問題になっているため、日頃の防カビ・除カビ対策が重要です
CSCの防カビ工法①
CSC独自の防カビ工法
CSC工法とは
カビを徹底除去した後に、防カビ剤をコーティングすることで長期間にわたりカビの発生を抑える CSC 独自の防カビ工法です。カビの除去だけでなく、そのほかの菌や汚れまでも同時に取り除くことができ非常に衛生的です。
シックハウス対策や喘息・アトピー性皮膚炎などの室内アレルギー性感染症の対策としても注目されています。

8つの特徴
●カビの徹底除去
胞子だけでなく、根深い菌糸も徹底除去。
一般の塩素系防カビ剤では処理しきれないカビも除去します。
●カビの長期発生を抑える
カビの完全除去と防カビコーティングにより、長期間の防カビ効果を実現。
●施工場所を選ばない
カビが壁の内部にまで侵食してない状況であれば、クロスを剥がすことなく除カビ・防カビコーティング処理が可能です。
●短期間で施工終了
足場を組まないので短期間で施工が完了します。
●消臭・防臭効果
防臭・消臭効果があるほか、散布された薬剤もニオイが気になりません。
●ダニ予防
ダニのみならず、ダニの卵まで分解除去。
●ニオイが気にならない
ニオイがほとんどないため、食品工場や飲食店でも安心です。
●体にやさしい安全な薬剤
厚生労働省が「快適で健康的な室内空気環境を確保すること」を目的に指針値を示している揮発性有機化合物(VOC)13物質を一切使用していません。
動画で見るCSC工法
もっと知りたい!CSC 工法の仕組み
特殊なゲルコーティングで湿度を調整
カビを除去したあと、特殊なゲル層でコーティングします。
水蒸気を通すが、水分は弾くという特性により、内部に水が溜まることを阻止すると同時に外部への揮発を促します。
また、周りに水滴を生じすぐに乾燥するため、長期間に渡ってカビの発生しにくい湿度を保つことが可能です。

CSC の防カビ工法②
防カビ性と安全性、どちらにもこだわった薬剤
表層洗浄処理
除菌能力と漂白能力の両方を併せ持つ薬剤を使用し、カビや微生物による汚染部位を同時に除去・漂白します。
深部殺菌処理
「抗菌防カビ被覆処理」前に、除菌状態を維持するため深部へ除菌処理を施します。
抗菌・防カビ被覆処理
抗菌・防カビ剤を被覆剤によって表面に固定し、長期にわたる抗菌・防カビ効果を発揮させます。
被覆処理を行うことにより、薬剤の溶解、溶出を防ぐとともに、カビの栄養源となる汚れやカビの胞子が付着することを防ぎます。壁、天井、床など住居全体を対象に処理します。
▶下地抗菌・防カビ処理
クロス、ボードなどを張る前の工程で、建物の骨格部分にあたる箇所に抗菌・防カビ処理を施します。
▶表層抗菌・防カビ処理
クロス、ボードなどを貼った上から仕上げの抗菌・防カビコーティングを施します。
薬剤の安全性
安心な環境は安全な施工から生まれます。
カビが無くなったといっても、強い薬剤によって別の薬害が生じるのでは意味がありません。
CSC 工法は、厚生労働省が「快適で健康的な室内空気環境を確保すること」を目的に指針値を示している揮発性有機化合物(VOC)13物質を一切使用しない安全安心の防カビ工法です。
また、LD50 と呼ばれる化学物質の毒性の強さを表す指標を用いた場合でも、薬剤の安全性が示されています。LD50 とは、「50% Lethal Dose(半数致死量)」のことで、ある化学物質を投与した場合に生物の半数(50%)が死亡する用量を「体重当たりの量(mg/kg)」で表した数値のことです。
下表のように、数値が大きいほど安全とされます。劇薬として知られる青酸カリの LD50 が 10mg/kg であるのに対し、当社の薬剤は 6000~20000mg/kg と高い安全性を誇っています。